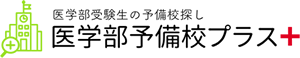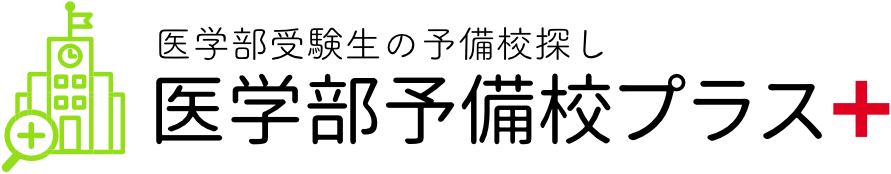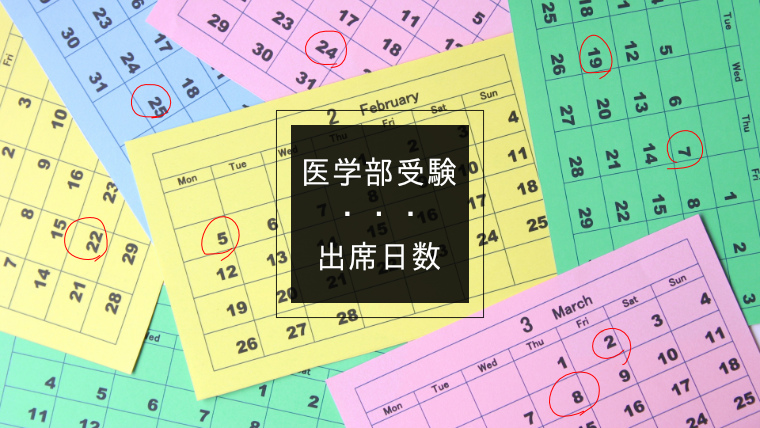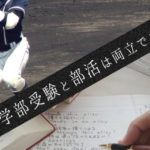近年、医学部入試の倍率は低下傾向にありますが、依然として入学難易度は高いままです。
理由としては上位層の不変、そして入試問題の難化などが挙げられます。しかし、そんな「難しい」医学部入試を突破するためには「出席日数」を過度に気にする必要はありません。
例え、出席日数が少なかったとしてもしっかりと医学部には合格することは可能です。
この記事ではその理由と、どういった対策をすればいいのかをお教えします。
1.医学部受験で出席日数は合否に全く関係ない理由
簡単に医学部受験で出席日数が合否に全く関係ない理由を列挙してみます。
(1)ほとんどの合否は一次試験(国公立の場合は筆記試験)で決まっている
(2)出席日数で合否を決めるメリットが大学側にない
(3)面接で深く突っ込まれる可能性も低い
それぞれ深掘りしていきます。
(1)ほとんどの合否は一次試験(国公立の場合は筆記試験)で決まっている
まずは、医学部受験におけるほとんどの合否が一次試験(国公立の場合は筆記試験)で決まっているということが理由の一つに挙げられます。
出席日数を合格の条件に含めているか否かは、大学側が正式に発表しているものがありません。そのため、確実にこうであるとは言えませんが、以下のような事例はどこの大学でもよく聞く事ができます。
【1】結構な手ごたえで一次試験を突破し、面接で失敗したが受かった
【2】まずまずの手ごたえで一次試験を突破したが面接で相当な手ごたえを感じたものの、最終的には不合格となった
【1】の場合は、一次試験が良かったため、面接が上手くいかなくとも受かった、というパターン。【2】の場合は面接試験で逆転したと思ったものの落ちてしまったパターン。
これらから読み取れるのは、やはり医学部受験では「一次試験(筆記試験)」の結果の方が大切であるということです。
(2)出席日数で合否を決めるメリットが大学側にない
次に、出席日数で合否を決めるメリットは大学にないということが挙げられます。
例えば、以下のような事例を考えてみると分かりやすいかもしれません。
『出席日数が足りていない不真面目な奴だから、成績は足りているが落とそう』と大学側が考えた場合、「合格点に達している優秀な人間」を切り落とすという大きな損失が発生します。
成績が足りているということはどんな形であれ、「努力できる素地がある」というように解釈されます。大学側としてはしっかりと大学に入ってからいい成績を残してくれる可能性を考慮し、出席日数には目をつぶるでしょう。
逆に、出席日数が足りておらず、一次試験も突破できないようであればこれは合格させるメリットが見当たりません。言わずもがなですが、医学を学ぶための学力(努力する力)が足りないと解釈されるためです。
(3)面接で深く突っ込まれる可能性も低い
一次試験を突破して二次試験に進んだ場合(国公立は大抵その日のうちに面接が行われるが)、ある程度の学力が担保されているということになります。
すなわち、「この人は医学部に入っても勉強についていける可能性が高い」と判断されているということです。つまり出席日数についてあえて深掘りする必要性は、本来大学側にはありません。
ですから、あえて出席日数を深く掘り下げる場合は以下のようなパターンしか考えられません。
【1】極度の反社会的精神疾患、障害を抱えているか否か
【2】受験生との「話題」作りの為
【1】の場合ですが、本当に一部の出席日数が足りていない人には、入学してもらっては困る極度の「反社会的な精神疾患・障害」を抱えている方がおられます。つまり、大学入学後に、大学運営に深刻な支障をきたしてしまうような方を見極めて、弾くために深く聞かれると考えられます。
しかしこういうケースはかなり稀であるため、極度に心配する必要性はありません。
実は、【2】の場合が大半で、単純になぜ休んでしまったのか、足りなかったのかを試験官が知りたいという場合が挙げられます。
この場合は純粋に言葉のキャッチボール(コミュニケーション)ができれば問題はないため、本当の理由をしっかりと自分の言葉で伝える必要性があります。応対の内容次第で合否が決まってしまうということは滅多にないと考えられるため、正直に話すことがベストでしょう。
2.医学部受験で出席日数が出願要件に入っている大学は?
(1)出席日数が出願要件に入っている大学はありません
結論から言ってしまうと、現時点で出願要件に「出席日数」が入っている大学はありません。
つまり、理論上は出席日数を満たしていなかったとしても、しっかりと一次試験(筆記試験)を突破できるだけの学力があれば、医学部に合格することは可能であると言うことができます。
(2)ただし、高校卒業以上の学力を有している必要はある
しかしながら、やはり「出席日数」がいくら合格に関係ないとは言え、出願要件には最低限の中等教育を受けているということが条件として挙げられます。
よくある提示例が「高校卒業同等以上の学力を有している」という文言です。
これは、大学によっても細かく異なりますが、普通に日本に暮らし、日本の高校(通信制含む)を卒業していれば簡単にクリアできます。
また、日本の高校を卒業していなかったとしても、大学側にそれだけの能力があると受験の前段階で認められれば普通に受験資格は得られると考えられます。(大学によって対応は異なります)
(3)合格最低点以上をたたき出せれば合格できる
ここまで述べてきた総括になりますが、結局のところ「出席日数」が足りていなかったとしても大学の一次試験(筆記試験)をクリアできれば、医学部には合格可能だと言うことができます。
つまり、これを読まれている皆さんが最初に気にすべきことは、「出席日数が足りるかどうか」ではなく、「一次試験を突破できるかどうか」であると言えますね。
3.出席日数を受験で不利にしないためのコツ
では、一次試験(筆記試験)を突破した後に、「出席日数」で不利にならずに二次試験(面接試験)を突破するためにはどうすれば良いのでしょうか?
その解が以下の3つになります。
(1)最後まであきらめないで挑戦すべし
(2)得意分野を伸ばすべし
(3)不利にしないためにアドバンテージをとる
それぞれ解説していきます。
(1)最後まであきらめないで挑戦しよう
まずは何事もそうですが、最後まであきらめずに挑戦することが大事です。
医学部に合格したい、そのために何を最初にすべきなのかと聞かれた場合、大半の医学生、そして医学部受験経験者は、「あきらめず最後まで粘る」ことであると答えます。
理由は単純で、最後まで努力した人にしか得られないものがあるということからです。
例えば、今回の記事のテーマのように「出席日数」がネックで、受からないかもしれないと思って弱気になってしまった場合、一番大事な一次試験(筆記試験)の勉強が疎かになり、その結果不合格になってしまうという大きなリスクが考えられますね。
この場合、最後まで筆記試験の勉強をしていれば、結果がどうなっていたかは分かりません。しかし、少なくとも、易々と一次試験で落とされてしまうということは、なかったかもしれません。
この記事では「出席日数」が合否には大きくは影響しないということを示したわけですから、しっかりと地に足を付けて、目の前の課題をこなしていくことが最適解でしょう。
(2)得意分野を伸ばす
次に、得意分野を伸ばしていくことも大きな合格への近道になるでしょう。
この記事を読まれている段階で、浪人生なのか現役生なのかに関係なく、やはり得意・不得意はあると思います。
数学の苦手意識がどうしても拭えない。英語の文法が全く理解できない。そういうものは、誰しも持ち合わせているものです。
しかし、これまた逆に不得意な科目を伸ばそうとすると、かなりの時間と労力を要してしまいます。
「不得意→できない→やる気が出ない→さらに不得意に」という悪循環にハマらないためにも、「苦手意識の払拭」は大事ですが、不得意を得意にする必要性はありません。
その点、得意な科目は苦手な科目に比べればとっつきやすいでしょうし、むしろ楽しいこともあるでしょうから、伸び率は高くなります。
本当に苦手な科目は、人並みにできるようになればいいのですから、あとは得意科目を伸ばすことに注力しましょう。
得意科目で高い点数をたたき出せるようになれば、一次試験の点数も高まり、結果的に出席日数が不利に働く可能性も低くなります。
(3)有利になるためにアドバンテージをとる
これは(1)、(2)の内容を要約したものになりますが、結局のところ一次試験の点数の高さが、受験生そのものの印象を大きく左右してしまいます。
したがって、もしも「出席日数」が心配であるならば、なおのこと一次試験で大きなアドバンテージを取りに行くのが得策でしょう。
「不利にならないために」というよりかは「有利にするために」良い点数、アドバンテージを狙いに行くという考え方が大事でしょう。
4.医学部受験で出席日数が足りるか心配な時にすべきこと
最後に、「出席日数」が心配ならすべきことを二つ挙げてみました。
ぜひ参考にしてみてください。
(1)大学の入試課に直接聞いてみる
真っ先にやるべきことは、実際に大学に電話をかけてみて本当に「出席日数」が不利にならないかを聞く事です。
この記事を含めて、ネットの記事や雑誌の情報をうのみにするのではなく、実際に自分の言葉で疑問を入試の実施者である大学に聞いてみるというのは本当に大切な行動になります。
もちろん、確実に返答があるとも限りませんが、不安を解消するには最も有効な方法と言えるでしょう。
(2)情報力を持った医学部専門予備校に相談する
困ったときの最終手段として覚えておいてほしいのは、医学部専門予備校に相談する、という方法です。
これは、医学部専門予備校には沢山の医学生(チューター)が所属していますし、現在進行形で最新の入試情報を分析している医学部受験の専門家が所属していますから、かなり豊富な入試情報が集まるためです。
例えば、どこの大学が入試方式を変えるであるとか、どこの大学が出願要件を変更しただとかは、医学部専門予備校に相談すれば一瞬で分かってしまいます。
頭の片隅にでも置いておくとよいかもしれませんね。
まとめ
この記事では、医学部受験に「出席日数」がほとんど関係ないということをお伝えしてきました。
もちろん、医学部受験をする上での心配は出席日数に限らず多数あると思います。
その中にあっても、やはり最後まであきらめずに挑戦し続けることができれば、確実に実りがあるでしょう。
この記事を読まれている皆さんが、来春に合格されていることをお祈りしております。